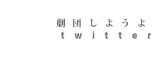幼児性と父性の格闘 -劇団しようよ『畦道』-
落 雅季子
『畦道』は、2020年初春に出された緊急事態宣言の下で、主宰・大原渉平の書きあげた新作戯曲である。これまで上演のための劇場や出演俳優を決めてから、俳優のために戯曲を書いてきた大原は、これからの演劇の上演形態がどうなるかもわからなかったあの宙に浮いたような日々を、この新作に費やした。
そんな戯曲が、人数を制限してのリーディングで上演されることになったと連絡を受けたのは緊急事態宣言の解除から長い梅雨を経て、オリンピックが中止された夏も過ぎ、秋が近づいてきた頃だっただろうか。 久しぶりに降り立った京都は観光客が激減し、住人だけが自転車で行き交うような街になっていた。烏丸通を折れて、夕暮れ時の高辻通を歩く。1階のファミマを目印に会場までの階段を上がる。すでに街中の洋品店などでは馴染みの光景となりつつあった検温、アルコール消毒を劇場の入口で私が受けたのは、この日が初めてだった。
両袖にパイプ椅子が並べられ、舞台奥にはギターアンプ。劇場には蛙の鳴き声が響いており、 それがかえって劇場の薄暗さと、感染症対策のために減らされた客席の寂しさを浮き上がらせていた。
▼リーディングとセッション
開演が迫り、俳優が全員、パイプ椅子に着席した。主人公にして語り手たるノリオ(藤原大介)は白いシャツにベージュのハーフパンツ、妹のみどり(岡田菜見)は黒いワンピース姿であり、残りの俳優は白いシャツと黒のボトムスで衣装を統一している。
おもむろにノリオが立ち「今、オレのことが見える人」と言った。『畦道』が、演劇作品としてスタートを切った瞬間だった。もちろん、見える。だってそこにいるのだから。ト書きを読むのにも俳優(西村花織)が割り当てられている。単なる読み合わせあるいは台本を手にもっての立ち稽古の域からどのように脱するかは、リーディング公演の起点であると同時に第一の難所でもある。実際のところは、俳優がト書きで読まれた指定の動きをまったくおこなわない(たとえばノリオは、ト書きが「ノリオ、そこから舞台中央を見つめる。」と言ったとしても舞台中央を見つめない)ことなどで、発話する主体として、俳優の緊張感を維持することに成功していた。
そして、台詞がそこで発話されることと同等に、本公演を演劇作品として「上演」たらしめていたのは、劇団しようよと活動を共にするミュージシャン吉見拓哉の存在であった。吉見は、俳優らの独白に重ねて、呻るようにギターを鳴らす。捻じれた残響音は不穏で、ぎょっとするほど雄弁でもある。物語冒頭、畦道でノリオが目撃した人外の黒い影たちの存在感は、ノリオの頭の中で人間とそうでないものの狭間にいる不気味なものとして物語全体を覆い続けたが、吉見の音楽もまた、そのように作品全体を包みながら、俳優たちと”セッション”をしていた。
▼上演の前提なき「執筆」
物語は早々に、ノリオの祖父が死んだことによって動き始め、ノリオの暮らす社会(たとえ田舎の狭いコミュニティであっても彼にとっては世界のすべてだ)の全容が明らかになってゆく。
ノリオの暴力を抑え込めない父親(土肥嬌也)と義母(中村こず恵)、障害を持っており自力で動くことのできない異母妹のみどり、「ガチャマニ」とノリオが呼ぶ不潔で得体の知れない男。とりわけこのガチャマニ(藤村弘二)の存在は重い。ノリオが祖父の死の間際に畦道で見た黒い人影は、見てはいけないとされる人外のものだったが、ガチャマニもそうした異形の腫れものとして描かれている。彼もみどりと同じく知的障害を持っているようで、ノリオの友人のひとりである東野(川崎未侑)に性的いたずらをしたこともあるらしい。彼はノリオたちのたまり場である駄菓子屋にしょっちゅうやってきては、ガチャポンを延々と回す。金は持っているのだ。年齢的にも、生殖能力を備えた男の欲望と身体を持っている。そのアンバランスさがノリオを、圧倒する。
みどりは、障害を持っていて口がきけない状態だと描写されるが、それでもノリオに語り掛けたり、時折りひとりごとを言うように台詞を発する。みどりを演じた岡田菜見(下鴨車窓)の、黒曜石のようなうつろな瞳、とろんとした話し方は、彼女がノリオたちとは異なる次元にいることを表しているようだった。ぞんざいな言葉遣いになりながらも、みどりを大切に思うノリオの心情はうつくしい。自分と同じ、何かが不完全であるという共感と、うっすら侮蔑も含められた愛情が見える。
物語が進むにつれ、ノリオの暴力性はどんどん露わになる。「家族なんてガチャポンのようなもの」「あんな親、ガチャポンで替えたったりたいわ」と言い切るノリオ。また、ガチャマニの異様な風貌の丹念な描写や、父親がコンバインで指を一本欠損させているという事実、生まれたときからの身体・知的障碍者とおぼしきみどりなど、リーディングではない形態の上演を考えると、具現化の心理的ハードルが高い設定が細かく描かれていることにも気づかされる。
ノリオはたびたび客席に「今、オレのこと、見える人」と問いかける。物語の後半で、彼はその役目を友人の蓮見(岩越信之介)に譲ったが、最後までその構造は続いた。裏には「オレのことが見えているとしたら、どのように?」という問いが隠れている。「見えないものを見えるようにふるまう」「本物ではない何かを別のものに見立てる」というのは演劇の魔法のひとつであるが、見えるか見えないか、ノリオと蓮見が問い続けたものとは何だったのだろう。まず、舞台上の虚構の存在である自分たち登場人物。俳優が演じるわけなので、これは視覚的には見えて当然なのだが、あらためて見えているかと俳優から問われると、観客は自分が今見ているのが誰か、何を表象しているのか、そもそも俳優の役柄を見るということは俳優を見ていることになるのかという幾重にも入れ子になった疑問を、瞬時に抱くことになる。繰り返し「今、あなたたちは何を見ているのか?」と問われることによって「もしかして(観客である)私たちは彼らをヒトとして見ていないのではないか?」という潜在意識を炙り出されるようで背筋が冷たくなった。
上演が前提になく、まず「執筆」に集中したことで、大原は俳優の技量や演出の技法を考慮せずに済んだ。「執筆ありき」という条件が、制約の多い登場人物の設定に大原を向かわせたことは意義深く思われる。
▼大人と子供の狭間で
冒頭で死んだおじいは、体も大きくスポーツもやり、恐らく農作業もタフにこなし、田舎における家父長制の長(おさ)として申し分なかっただろう。ノリオはおじいを憎んでいたが、決して勝てない存在であるという屈折した感情も抱えていた。
ノリオ「現にみどりは、ニンゲンの形をせず生まれてきた。オレが言うたんちゃう。おじいが言うた。はっきり言うた。オレは聞いた。(中略)オレらは人間になりたい。ニンゲンの形をしたい。田んぼの真ん中で踊る、回る、彼らは何?みどりか。オレか。おじい、言えよ。言って死ねよ。」
前時代的な「父権的」強さを持つおじいに反発するノリオが、無意識のうちに憧憬を抱いているものは「父性」である。ここで言う父性とは(性別によるものではなく)他者の弱さに目を配り、威圧感によらない秩序を自分のなわばりにもたらせること、その能力を周囲から認められた存在であることと定義したい。そしてノリオは、ガチャマニとみどりを交わらせて新しいニンゲンを作ろうという行動に出る。ノリオはまだ幼く、みどりと子どもを成すことができないからだ。ノリオの中では、ガキ大将としてみんなを守ろうとし、みどりを大切に思う父性と、短絡的な幼児性がせめぎあっている。幼児性とは、思い通りにいかない現実に憤って暴力をふるったり、駄々をこね、自分本位に相手を動かそうとする欲求のことだ。
みどりと友人を連れてガチャマニのもとへ向かったノリオは、彼に相撲を挑み、負ける。ノリオもガチャマニも、地元において、おじいのような父権的な強さ(先ほどの父性とは区別して用いる)を、他者からは認められない人物である。ノリオのように体格がよく喧嘩が強くてもだめ。ガチャマニのように有り余る金を使ってガチャポンを昼間から好き放題回していても、この社会ではだめだ。ノリオは、おのれの幼児性と父性のぶつかり合いを体験し、その混乱からガチャマニに投げ飛ばされて井戸に落ちてしまった。
戯曲としては、ややぎこちない筆致の展開だったが、それは大原自身も父権的なるものへの反発、そして憧れを持て余しているからではないだろうか。「もしかして自分も父権的な強さを目指さなくてはいけないのか?」という劇作家の葛藤が、行間にまぶされているのを感じる。
井戸に落ちたノリオは、その中でみどりと溶け合う。混沌とした生命のスープの中で、ノリオとみどりは光の粒子になって新しい命を生んだ。人はどんな姿であっても、この世界でみずからの生をまっとうする権利を持つと私は考える。何らかの欠損を持つ人が心無い言葉を投げかけられたり、存在を無視されたりすることなく、人間の形の「個別の違い」に対応できない今の未成熟な社会が変わってほしい。だが閉塞的な田舎では、その考え方を貫くことが難しいことも想像できるし、ノリオは「ニンゲン」が「人間」の形をしていなくても、存在としてどこまで有効なのか思考しないと気が済まないようなのだ。
ノリオ「なんの形しとったら人間や。なんの形しとったらそうじゃないんや、おじい」
その叫びを聞いたとき、これまで私が劇団しようよの作風を支えていると感じていた童話的な優しさは、大原の中にある禍々しい想像力を覆い隠すものだったのかもしれないと思った。コロナ禍の緊急事態宣言下における孤独な内省期間は、大原の倫理観のたがを外したようであった。あらゆる芸術・エンターテインメントが一時停滞を余儀なくされた2020年だったが、この新しい挑戦を板の上に乗せたいという、渇望に満ちた演劇空間に立ち会えたことが、私は喜ばしかった。
蓮見「…あの、見える人。新しい国が。新しい子供が。新しいニンゲンが。誰か、いませんか。」
最後の音が消え、アンプの明滅する光だけが暗転の中に残った。明かりのついた劇場に、ふたたび蛙の鳴き声が響く。『畦道』というタイトルのとおり、このリーディング公演は、作り手も観客も、ともに泥の中に分け入るように進んでいく生々しさがあった。いずれ戯曲はリライトされるかもしれない。フルサイズでの上演が決まり、演出プランが練られる日が来るかもしれない。可能性の井戸の中で、『畦道』はまた新しく生まれるのを、待っている。
落 雅季子
1983年東京生まれ。批評家。LittleSophy主宰。2009年から演劇・ダンス批評を始め、2017年からは文体と拮抗する身体の獲得のため、クラシックバレエの学びを行なっている。
Twitter:@maki_co
2011-2017 Copyright ©劇団しようよ All Rights Reserved.